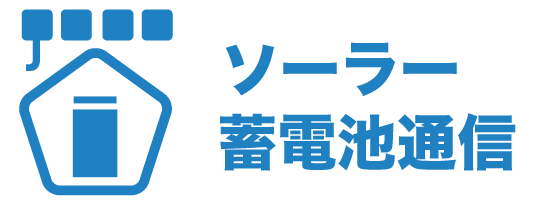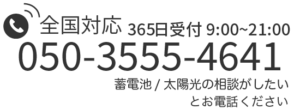突然の停電。夜になると、明かりがないだけで家の中は一気に不安になります。地震や台風などの災害時には、復旧までに時間がかかることもあり、家庭でも最低限の照明を確保しておくことが大切です。
そんなときに活躍するのが「LEDランタン」。懐中電灯とは違い、広範囲を照らすことができ、両手が使えるのも魅力です。
この記事では、停電や災害時に役立つLEDランタンの選び方と、家庭で使いやすいポイントをわかりやすくご紹介します。非常時に備えて、「明かり」の準備を見直してみませんか?
停電時に明かりがないと、何が困る?
停電が起きると、まず困るのが明かりの確保です。夕方以降は思っている以上に早く暗くなり、照明が使えないと、家の中の移動だけでも危険が伴います。つまずいたり、物にぶつかったりして、思わぬケガをするおそれがあります。
とくにトイレや階段、玄関まわりなど、もともと足元が暗くなりがちな場所では注意が必要です。また、明かりがないことで家族の不安も大きくなります。小さなお子さんや高齢の方がいるご家庭では、暗闇そのものが強いストレスにつながることもあります。
料理や片付け、避難準備など、手元の作業にも支障が出ます。
懐中電灯やスマートフォンのライトでは、照らせる範囲が限られてしまい、光も一方向に集中しがちです。部屋全体をやわらかく照らすような明るさは得られず、両手もふさがるため、長時間の使用には向いていません。さらに、スマートフォンはバッテリー切れの心配もあります。
こうした事態に備えて、停電時でも家族全員が安心して過ごせる明かりを、あらかじめ用意しておくことが大切です。
LEDランタンが防災に選ばれる理由とは?停電時に役立つ3つの特長
停電時の明かりとして、LEDランタンが防災用に選ばれる理由には、いくつかの特長があります。ここでは、実際に非常時に役立つ3つのポイントにしぼってご紹介します。
【1】広範囲を照らすやわらかい明かり
懐中電灯のように一方向だけを照らすのではなく、LEDランタンは360度に近い範囲を明るく照らすことができます。部屋の中央に置けば、家族全員が視界を確保しやすく、作業や移動も安心です。強い光ではなく、やわらかい光で目にもやさしいのが特徴です。
【2】両手が自由に使える設置スタイル
ランタンは床やテーブルに置けるだけでなく、吊り下げたりスタンドに固定したりと、状況に応じて使いやすいのが利点です。両手が空くため、調理・着替え・避難準備など、日常的な動作を妨げません。複数の設置場所に分けて使えるモデルもあり、安心感が広がります。
【3】電源方式の選択肢が豊富
LEDランタンには乾電池式・充電式・ソーラー対応など、さまざまな電源方式があります。電池が手に入らない状況でも、USB充電や太陽光で使えるタイプを選んでおけば、より長く安心して使い続けることができます。停電が長引く場合の備えとしても非常に有効です。
このように、LEDランタンは非常時の明かりとして、使いやすさと実用性のバランスに優れたアイテムです。次の章では、家庭で実際に選ぶときのポイントについて見ていきましょう。
失敗しないLEDランタンの選び方|防災用で押さえたいポイントとは
LEDランタンは種類が多く、見た目や価格もさまざまです。防災のために備えておくなら、いざという時に本当に使いやすいかどうかを意識して選ぶことが大切です。以下のポイントを確認しておくと、停電時にも落ち着いて対応できます。
【明るさと光の色味】
停電時に1部屋を照らすには、300〜500ルーメン程度の明るさが目安になります。ただし、明るさだけでなく「光の色味」も大切です。白くて強い光は見やすい反面、長時間使うとまぶしさや疲れを感じることがあります。あたたかみのある電球色を選ぶと、夜間でも落ち着いて過ごしやすくなります。
製品によっては、明るさを調整できるものもあるので、ご家庭の使い方に合ったモデルを選ぶと安心です。
【点灯時間】
停電がどれくらい続くかは、災害の規模や復旧状況によって大きく変わります。そのため、LEDランタンは長時間しっかり使えることが非常に重要です。最低でも8時間以上の連続点灯が可能なものを選ぶと安心です。
できれば、明るさを切り替えられる機能があるタイプを選ぶと、状況に応じて光を抑えながら電池を長持ちさせることができます。また、防災用として備えるなら、信頼できるメーカーの製品を選ぶことも大切です。
簡易な100円ショップのライトなどは、連続使用に耐えられなかったり、途中で不具合が起きたりすることもあるため、非常時には不安が残ります。いざというときにきちんと使える、品質面で安心できる製品を選びましょう。
【電源方式】
防災用にLEDランタンを備えるなら、「どんな電源で使えるか」だけでなく、「停電時にどう充電するか」も大切な視点です。
もっともおすすめなのは、モバイルバッテリー機能を備えた充電式LEDランタンです。
充電式LEDランタンとは
モバイルバッテリー機能付きLEDランタン
本体にUSB出力ポート(多くはUSB-A)を備えたランタン
停電時にスマートフォンや小型機器への給電が可能「照明」と「充電器」を兼ねた防災アイテム
よくある仕様:
例)「リチウム電池内蔵 3,600mAh」「USB出力5V/500mA」など
これは明かりとして使えるだけでなく、スマートフォンなどの機器に給電できるタイプで、災害時には1台で明かりと電源の両方をカバーできます。スマホの充電は連絡や情報収集のためにも欠かせないため、防災用品として非常に実用的です。ただし、こうした機能がない一般的な充電式ランタンを選ぶ場合は、モバイルバッテリーが必須になります。
充電式ランタンはコンセントが使えないと電源の確保が難しいため、あわせてモバイルバッテリーやポータブル電源を用意しておくことで、停電が長引いても安心です。
さらに備えを万全にしておきたい場合は、乾電池で使えるタイプや複数の充電式LEDランタンを備えておくとより安心です。充電が切れたときの予備として使えたり、部屋ごとに分けて設置することもできるため、実際の停電時に役立ちます。
LEDランタンだけでは不安?停電が長引くときの電源対策とは
LEDランタンは、停電時の明かりとして非常に頼れるアイテムです。ただ、明かりだけではすべての不便を解消できるわけではありません。災害が長引くと、照明以外にもさまざまな「電気」が必要になる場面が出てきます。
たとえば、冷蔵庫の中身を守ったり、スマートフォンを充電したり、冬場であれば電気毛布や暖房器具を使う必要があるかもしれません。こうした生活に欠かせない家電製品は、LEDランタンではまかなえないため、別の「電源の備え」が重要になります。
実際に、地震や台風などで数日間の停電が起きた地域では、「明かりはあるけど、電気が使えなくて困った」という声が多く聞かれました。非常時に本当に安心できる環境を整えるには、「明かり」だけでなく、「電気そのもの」をどう確保するかが大きなカギとなります。
非常時、大切な人を守るには?太陽光発電と蓄電池の選択肢
災害時にもっとも守りたいのは、大切な家族の命と暮らしです。とくに小さなお子さんや高齢の方がいるご家庭では、停電が長引くほど心身への負担が大きくなります。たとえば真夏や真冬の停電では、エアコンや暖房器具が使えず、体調を崩すリスクも高まります。冷蔵庫の中身が傷んだり、スマートフォンが充電できなかったりと、日常の安心が徐々に失われていくのも現実です。
太陽光発電があれば、晴れていれば日中に「自立運転モード」に切り替えて電気を使うことができます。ただし、曇りや雨で発電量が少ない日や、日が暮れてしまった後は、太陽光発電システム自体が発電を停止してしまうため、電気をまったく使えなくなります。
家庭用蓄電池があれば、太陽光で発電した電気をためておくことができ、停電時に電力を確保できます。照明、冷蔵庫、スマートフォンの充電、エアコンや給湯器が利用でき蓄電池は非常に心強い備えです。
すでに太陽光発電を設置している方はもちろん、これから導入を検討する方にとっても、「太陽光+蓄電池」の組み合わせは、家族を守る安心のセットといえるでしょう。防災対策として、本格的に検討する価値は十分にあります。
ご家庭に合った電気の備え方とは?まずは無料で相談してみませんか
災害時の備えとして、どのような「電気の確保」が自分の家庭に合っているのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。ご家庭の状況や家族構成、これまでの設備に応じて、選ぶべき備え方は変わってきます。
太陽光発電をまだ設置していないご家庭であれば、「太陽光発電+蓄電池」を同時に導入することで、日中は太陽の光で発電し、夜間や停電時は蓄電池から電気を使う、という自立した電気の循環が可能になります。国や自治体の補助金制度を活用すれば、初期費用の負担も大きく軽減できるため、実際に導入される方も増えています。
すでに太陽光発電を設置されているご家庭であれば、蓄電池を後付けすることで、発電した電気を無駄なく活用できるようになります。とくに停電時には、蓄電池があることで家全体の照明や冷蔵庫など、生活に必要な電気を自動でバックアップできます。電気代の削減にもつながるため、非常時だけでなく日常の安心にもつながります。
どのような設備がご家庭に合っているかは、屋根の広さや築年数、現在の契約プランによっても異なります。まずは無料で、お気軽にご相談ください。専門スタッフが一軒一軒の状況に合わせて、わかりやすくご提案いたします。

監修者プロフィール
蓄電池・太陽光アドバイザー 内田 博己
株式会社ジャパン電気
代表取締役/第二種電気工事士
太陽光業界で15年以上の実績。蓄電池・太陽光の販売・保守・修理対応に精通し、全国のご相談をサポートしています。
国家資格「第二種電気工事士」保有。